生命医科学研究科 ティッシュエンジニアリング研究室を修了した松本紗季さん(2019年3月修了)らの研究成果が、日本眼科学会の国際誌「Japanese Journal of Ophthalmology」に掲載されました。
本研究は、角膜内皮の難治性疾患であるフックス角膜内皮ジストロフィ(FECD)の新たな病態メカニズムを解明したものです。FECDは加齢とともに進行し、視力が低下して失明に至ることもある疾患で、角膜移植が唯一の根本的治療法とされています。
研究チームは、患者さんから提供された角膜組織や疾患モデル細胞を用いて詳細な解析を行いました。その結果、細胞内で「小胞体」と「ミトコンドリア」というふたつの重要な細胞小器官が異常に強く結合していること(MAMsの形成亢進)を世界で初めて発見しました。この異常な結合は、タンパク質の折り畳み不全によって引き起こされる「小胞体ストレス」と深く関係しており、最終的に細胞死や角膜障害に関係する可能性が示されました。
この成果により、これまで不明だった「なぜ角膜内皮細胞が徐々に壊れていくのか」という疑問に対して新しい仮説が提示されました。今後、この知見を活かして「小胞体とミトコンドリアの異常な結合を抑える薬剤」の開発につながる可能性があります。

【松本紗季さんのコメント】
「大学院での研究を通じて、フックス角膜内皮ジストロフィ(FECD)という難治性の角膜疾患において、細胞内で小胞体とミトコンドリアが異常に強く結びついていることを世界で初めて明らかにしました。この異常な結合が、角膜内皮細胞の死に関係している可能性があることが分かりました。今回の成果は、これまで治療法が角膜移植に限られていたFECDに対して、新しい薬による治療法開発の足がかりになると考えています。研究を支えてくださった先生方や共同研究者の皆様、そして貴重な角膜組織を提供してくださった患者さんに心から感謝いたします。」
論文情報
タイトル
Enhanced Mitochondria-Associated Membrane Formation in Fuchs Endothelial Corneal Dystrophy: A Novel Link Between Endoplasmic Reticulum Stress and Mitochondrial Dysfunction
著者
Saki Matsumoto¹, Saori Kadoya¹, Yuna Horiuchi¹, Hirokazu Okuda¹, Keita Miyadai¹, Yu Shima¹, Robert D. Young², Andrew J. Quantock², Ursula Schlötzer-Schrehardt³, Friedrich Kruse³, Noriko Koizumi¹, Naoki Okumura¹
- 1. 同志社大学
- 2. カーディフ大学(英国)
- 3. エアランゲン=ニュルンベルク大学(ドイツ)
| お問い合わせ |
生命医科学部・生命医科学研究科事務室 TEL:0774-65-6020
|
|---|
2025年10月10-12日に開催された第85回日本動物心理学会大会において、奈良紫月さん(生命医科学研究科 医工学・医情報学専攻 脳神経行動工学研究室)が優秀発表奨励賞を受賞しました。
本賞は、若手研究者を育成しその研究を奨励するため、優れた口頭発表を行った博士の学位取得後3年以内までの会員に授与されるものです。
奈良さんは、アブラコウモリの養育行動に着目し、仔が発する isolation call が母親の行動を誘発する重要な因子であることを明らかにしました。さらに、母親の反応は接触刺激を通じて知覚される仔の喪失によって制御されることが示唆されました。
これらの結果は、アブラコウモリにおける選択的かつ柔軟な育児戦略の存在を示すものです。

発表題目
Motivational trigger cues in maternal behavior in Japanese house bat
発表者(受賞者)
奈良 紫月(生命医科学研究科 医工学・医情報学専攻 博士課程(前期課程) 2年次生)
連名者
橋澤(吉野) 寿紀(東京科学大学生命理工学院 日本学術振興会特別研究員(生命医科学研究科 博士課程(後期課程) 2024年9月修了))
小林 耕太(生命医科学部 医情報学科 教授)
飛龍 志津子(生命医科学部 医情報学科 教授)
| お問い合わせ |
生命医科学部・生命医科学研究科事務室 TEL:0774-65-6020
|
|---|
生命医科学研究科 医工学・医情報学専攻 ヒューマンインフォマティクス研究室 山本達也さん(2023年度修了)、杉浦知さん、日和悟教授、廣安知之教授らの研究成果が、Network Neuroscience誌に掲載されました。
私たちの脳は、神経細胞同士がつながってできた「ネットワーク構造」によって情報を処理しています。この結びつきのことを「脳の構造的結合(structural connectivity)」と呼びます。近年、MRIなどの計測技術を使って脳のネットワークを解析し、認知機能や精神疾患との関わりを理解しようという研究が進められています。しかし、1回の実験にかかる時間や制約の都合上、十分な数のデータを集めることが難しいという大きな課題があります。
今回の研究では、この「データ不足」の課題を解決するために、人工知能の一種である生成モデル(Generative Adversarial Network: GAN)を用いて人工データを生成する方法を開発しました。通常のGANは「本物らしいデータ」を作ることに特化していますが、本研究ではさらに「認知課題との関連性が保たれるように」データを作り出す工夫を加えました。その結果、実際の脳データに近いだけでなく、認知機能とのつながりを反映した人工データを大量に作り出すことに成功しました。これは、人工的に作り出したデータを用いて研究を補強できる可能性を示しており、今後の脳科学研究やAIによる認知機能予測の精度向上に役立つと期待されます。
研究内容の詳細は以下の関連情報をご覧ください。
関連情報
論文タイトル
Task-guided generative adversarial networks for synthesizing and augmenting structural connectivity matrices for connectivity-based prediction
著者
Yamamoto T., Sugiura S., Hiroyasu T. and Hiwa S.**Corresponding author
雑誌
Network Neuroscience 2025; 9 (3): 1110–1137.
doi:https://doi.org/10.1162/NETN.a.24
| お問い合わせ |
生命医科学部・生命医科学研究科事務室 TEL:0774-65-6020
|
|---|
生命医科学研究科 ティッシュエンジニアリング研究室の赤木歩さん(2025年3月修了)らの研究成果が、日本眼科学会の公式英文誌「Japanese Journal of Ophthalmology」に掲載されました。
本研究は、島根大学医学部眼科学講座 谷戸正樹教授との共同研究による成果です。
緑内障は眼圧が上昇することで視神経が障害され、世界的に失明原因の上位を占める疾患です。治療の基本は眼圧を下げることですが、眼圧が十分にコントロールされても視野障害が進行する患者が少なくありません。そのため、血圧や血流といった血管因子が関与している可能性が指摘されてきました。
研究チームは、島根大学医学部附属病院に通院した緑内障患者1,634名の電子カルテ36,561件から、眼圧や血圧、投薬など216項目の臨床データを自然言語処理で自動抽出し、428名(POAG 295名、EXG 133名)を解析対象としました。
その結果、眼圧や血圧が厳格に管理された環境では、眼灌流圧(ocular perfusion pressure: OPP)は視野進行の有意な予測因子とはならず、代わりに高齢、初期の視野障害の重症度、使用薬剤数など従来の臨床因子がより強く関連していることが示されました。これは、血管因子の関与を否定するものではなく、日常診療で測定される血圧・眼圧の範囲内では予測力が限定的であることを示しています。
本成果は、緑内障管理において依然として眼圧コントロールが最重要である一方で、AIを活用した電子カルテ解析が大規模・高精度な臨床研究を可能にすることを示した点でも意義深いものです。

「本研究では、自然言語処理技術を用いることで、膨大な電子カルテデータを効率的に解析し、緑内障進行の因子を明らかにすることができました。予想に反して眼灌流圧の影響は限定的であることがわかり、眼圧管理の重要性を再確認するとともに、AI技術が臨床研究に強力なツールとなり得ることを実感しました。」
論文情報
タイトル
Role of perfusion-related metrics in visual field progression of primary open-angle and exfoliation glaucoma: a natural language processing approach
著者
Ayumu Akagi¹, Kaito Narimoto¹, Kanta Ueda¹, Noriko Koizumi¹, Naoki Okumura¹*, Masaki Tanito²
*責任著者
1. 同志社大学 2. 島根大学
掲載紙
| お問い合わせ |
生命医科学部・生命医科学研究科事務室 TEL:0774-65-6020
|
|---|
2025年3月17-19日に行われた日本音響学会2025年春季研究発表会において、大西優衣さん(生命医科学研究科 医工学・医情報学専攻 脳神経行動工学研究室)が学生優秀発表賞を受賞しました。本賞は、将来の音響学の発展を担う若手研究者を奨励するため、春季又は秋季研究発表会において優秀な発表を行った学生会員に贈呈されます。大西さんは、モモジロコウモリの採餌場面における音声コミュニケーションに着目し、音響と映像の同期計測を行いました。その分析から、採餌中に交わされる発声の中に、状況に応じて異なる社会的文脈を持つことが明らかになりました。この研究は、コウモリの音声の機能を理解し、社会性やコミュニケーションの仕組みの新たな理解につながるといえます。
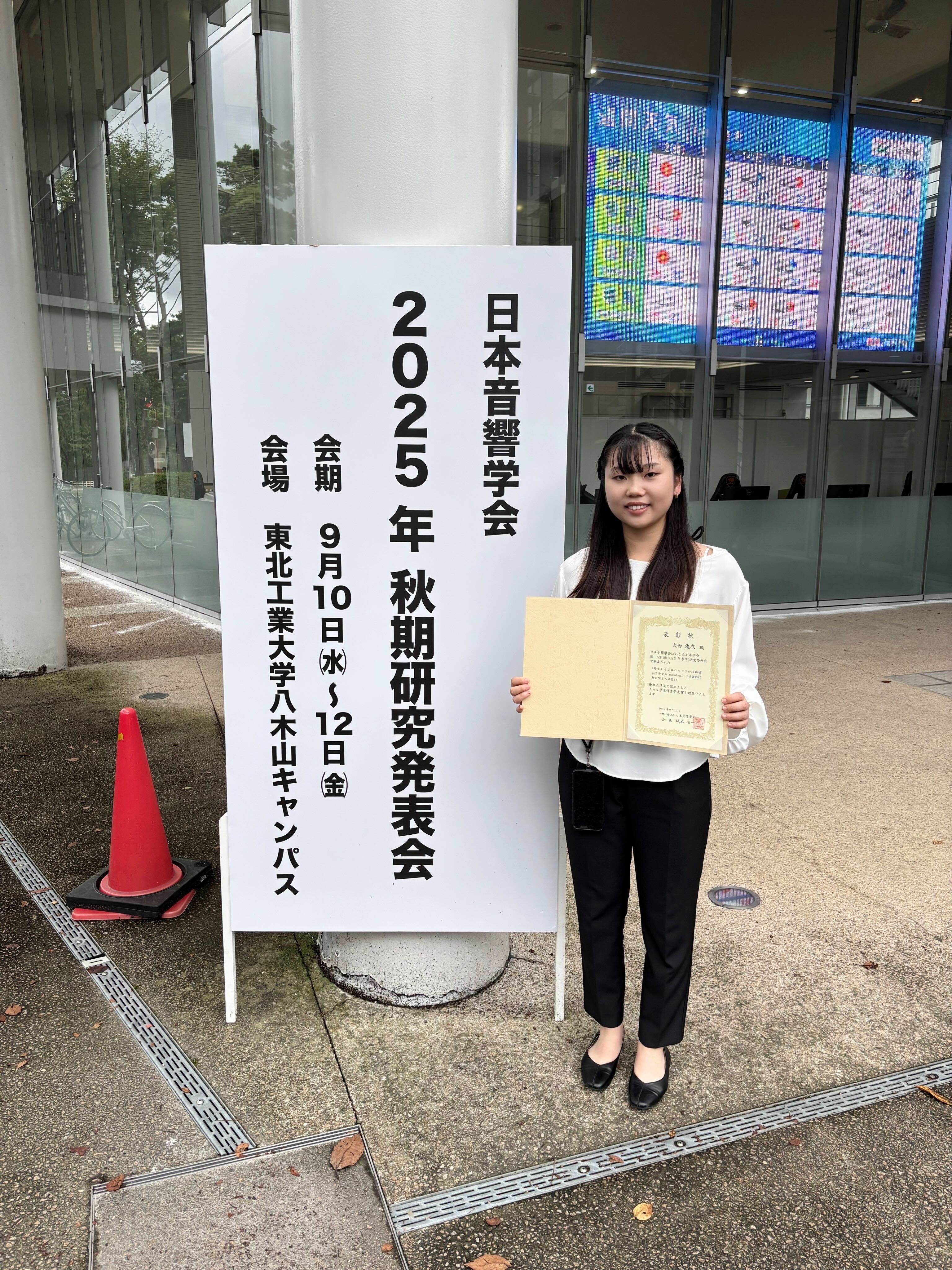
発表題目
「野生モモジロコウモリが採餌場面で発するsocial callと社会的行動に関する分析」
受賞者
大西 優衣(生命医科学研究科 医工学・医情報学専攻 博士課程(前期課程) 2年次生)
連名者
平尾 碧大 (生命医科学研究科 医工学・医情報学専攻 博士課程(前期課程) 2025年3月修了)
坂本 翼 (生命医科学部 医情報学科 2025年3月卒業)
藤岡 慧明 (同志社大学 研究開発推進機構)
福井 大 (東京大学大学院 農学生命科学研究科 講師)
飛龍 志津子(生命医科学部 医情報学科 教授)
| お問い合わせ |
生命医科学部・生命医科学研究科事務室 TEL:0774-65-6020
|
|---|
成績評価に対して採点質問・異議申し立てをしたい場合は、成心館1階教務センター(生命医科学部)にて採点質問票を受け取り、以下の要領で提出してください。
受付期間
2025年9月12日(金) ~ 9月19日(金)17:00
※受付は事務室開室時間内(9:00~11:30、12:30~17:00)に限ります。
受付場所
成心館1階教務センター(生命医科学部)※対面でのみ受け付けます。
提出時の注意事項
- 受付期間終了後は、いかなる理由があっても受付できません。
- 採点質問票には、採点質問を行う具体的な理由を記入してください。理由が不明瞭であったり、採点質問票の趣旨にそぐわない内容(嘆願文、他の学生との比較など)と事務室が判断した場合は、書き直しをお願いすることがあります。
- 複数の科目に対して採点質問を行う場合は、科目ごとに採点質問票を提出してください。
| お問い合わせ |
生命医科学部・生命医科学研究科事務室 TEL:0774-65-6020
|
|---|
生命医科学研究科 ティッシュエンジニアリング研究室の大西貴子さん(2021年3月修了)らの研究成果が、「Investigative Ophthalmology & Visual Science」に掲載されました。
このたび、本学の研究グループは、角膜移植の原因の約40%を占める眼疾患であるフックス角膜内皮ジストロフィ(FECD)において、細胞死を防ぐ新たな治療標的を初めて発見しました。本研究は、Erlangen大学(ドイツ)との共同研究による成果です。
FECDは、角膜内皮細胞が徐々に減少し、角膜が白く濁ることで視力が低下する病気です。現在、重症例に対する治療法は角膜移植しかありませんが、ドナー不足が世界的な問題となっています。
研究グループは、FECD患者由来の細胞と複数の実験モデルを用いて、細胞内ストレスによる細胞死のメカニズムを解析しました。その結果、「p38 MAPK」というタンパク質が、細胞のストレス応答から細胞死に至る過程で重要な「分子スイッチ」として働いていることを発見しました。さらに、p38 MAPKの働きを阻害する薬剤により、角膜内皮細胞の細胞死を防ぐことに成功しました。今回の研究成果は、FECDの病態メカニズムの解明に貢献するだけでなく、角膜移植に代わる新たな薬物治療の開発につながる重要な発見であると考えています。
コンテンツビルダー上で、ここのテキストを差し替えてください。テキストの貼り付け(ペースト)する際は、[Ctrl]+[Shift]+[V]のショートカットを使って、プレーンテキストとして貼り付けてください。

【大西貴子さんのコメント】
FECDは角膜移植を必要とする主要な原因疾患でありながら、その病態メカニズムには不明な点が多く残されていました。特に、細胞内のストレスがどのようにして細胞死へと至るのか、その分子経路の解明は長年の課題でした。本研究では、p38 MAPKというタンパク質が、ストレス応答から細胞死への重要な「分子スイッチ」として機能していることを明らかにしました。
最も印象的だったのは、複数の異なる実験モデルすべてにおいて、p38 MAPKの阻害が一貫して細胞保護効果を示したことです。基礎研究では、一つの発見が本当に意味を持つのか、常に慎重な検証が必要ですが、今回の結果は非常に再現性が高く、将来の治療応用への確かな手応えを感じることができました。
本研究の成果は、新しい治療薬の開発に繋がり、患者さんへの恩恵をもたらす可能性があります。基礎研究が臨床応用へとつながる道筋を示せたことは、大きな喜びです。
本研究の詳細な内容は、以下をご覧ください。
タイトル
The PERK-p38 MAPK Axis Drives Endoplasmic Reticulum Stress-Induced Apoptosis in Fuchs Endothelial Corneal Dystrophy
著者
Takako Onishi, Taichi Yuasa, Naoyuki Ueda, Keita Miyadai, Theofilos Tourtas, Ursula Schlötzer-Schrehardt, Friedrich Kruse, Noriko Koizumi, and Naoki Okumura
関連情報
| お問い合わせ |
生命医科学部・生命医科学研究科事務室 TEL:0774-65-6020
|
|---|
生命医科学研究科 ティッシュエンジニアリング研究室の赤木歩さん(2025年3月修了)らの研究成果が、「Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology」に掲載されました。
本研究は、島根大学医学部眼科学講座 谷戸正樹教授との共同研究による成果です。
本研究は、緑内障手術後の角膜内皮細胞への長期的な影響を調査したものです。
緑内障は眼圧が上昇することで視神経が障害される病気で、治療として眼圧を下げる手術(濾過手術)が行われることがあります。この手術は眼圧を効果的に下げることができますが、角膜の内側にある内皮細胞への影響が懸念されています。角膜内皮細胞は角膜の透明性を保つ重要な細胞で、一度失われると再生しません。
研究チームは、濾過手術を受けた136名の患者さんのデータを分析しました。特筆すべきは、電子カルテに記載された文章を自然言語処理技術を用いて、36,561回分の診察記録から必要な情報を抽出・解析したことです。これにより、従来は困難だった大規模かつ長期的なデータ分析が可能になりました。
研究の結果、手術後約1,500日にわたって、角膜内皮細胞は100日あたり約1%の割合で徐々に減少することが明らかになりました。また、手術後の眼圧が低い患者さんほど、内皮細胞の減少が大きいという予想外の発見もありました。
この研究成果は、緑内障手術後の患者さんの長期的な管理において重要な知見が得られたことに加えて、電子カルテの自動解析技術を活用した医療データ研究の新たな可能性を示した点でも意義深い研究となりました。

【赤木歩さんのコメント】
「私たちの研究では、緑内障手術を受けた患者さんの長期的な経過を、電子カルテの自動解析技術を用いて詳しく調査しました。4年以上にわたる追跡調査の結果、手術後の眼圧が低い患者さんほど角膜内皮細胞の減少が大きいという、これまで知られていなかった重要な発見をすることができました。この研究成果は、手術後の患者さんの管理方法を改善し、より良い治療成果につながることを期待しています。また、自然言語処理技術を医療研究に応用するという新しい手法を確立できたことも大きな成果だと考えています。現在は社会人として働いていますが、大学院で学んだデータ解析の手法や研究における論理的思考は、日々の業務においても大変役立っていると感じています。ご指導いただいた先生方、共同研究者の皆様、そして研究にご協力いただいた患者さんに心より感謝申し上げます。」
論文情報
タイトル
Long-term corneal endothelial cell loss after filtration surgery: Analysis using natural language processing
著者
Ayumu Akagi1, Kaito Narimoto1, Kanta Ueda1, Noriko Koizumi1, Naoki Okumura1*, and Masaki Tanito2*
1. 同志社大学 2. 島根大学
*共同責任著者
関連情報
| お問い合わせ |
生命医科学部・生命医科学研究科事務室 TEL:0774-65-6020
|
|---|
生命医科学研究科 ティッシュエンジニアリング研究室の中村優斗さん、兼松悠真さんらの研究成果が「Computers in Biology and Medicine」に掲載されました。
このたび、本学の研究グループは京都府立医科大学 眼科学教室(視覚機能再生外科学)との共同研究により、眼窩骨折をCT画像から自動的に検出し、緊急手術が必要なタイプを判別する人工知能(AI)システムの開発に成功しました。本研究は眼形成の専門家である、京都府立医科大学の奥拓明医師、渡辺彰英医師らとの共同研究として行われました。
眼窩骨折は、眼球を収める骨(眼窩)が外傷により折れる怪我で、特に「閉鎖型」と呼ばれるタイプは、眼球を動かす筋肉が骨折部位に挟まれるため、緊急手術が必要です。しかし、CT画像での診断は専門的な知識を要し、見逃されると視力障害や複視(物が二重に見える)などの後遺症を残すことがあります。
研究グループは、686名の眼窩骨折患者のCT画像(約46,000枚)を用いて、2段階の深層学習システムを開発しました。第1段階では骨折の有無を検出し、第2段階では骨折のタイプ(閉鎖型または開放型)を判別します。その結果、患者レベルでの骨折検出率は94.7%、閉鎖型の判別精度は100%という高い性能を達成しました。
今回の研究成果は、専門医が不在の救急外来や地域医療において、緊急手術が必要な眼窩骨折を見逃すリスクを大幅に減らし、患者の視機能を守ることにつながる重要な技術開発であると考えています。

【中村優斗さんのコメント】
この度、修士課程での研究を論文として掲載できることを心より嬉しく思います。医療AI分野での研究を通じて、技術により患者さんの未来に貢献できる可能性を実感する貴重な経験となりました。研究を進める中で、異なる専門分野の方々との協働を通じて多角的な視点を身につけることができ、今後の人生において財産になると考えています。本研究をさらに発展させ、実際の医療現場において診断支援ツールとして広く活用されることを目指したいと思います。最後に、本研究に関わってくださったすべての方々に心より感謝申し上げます。
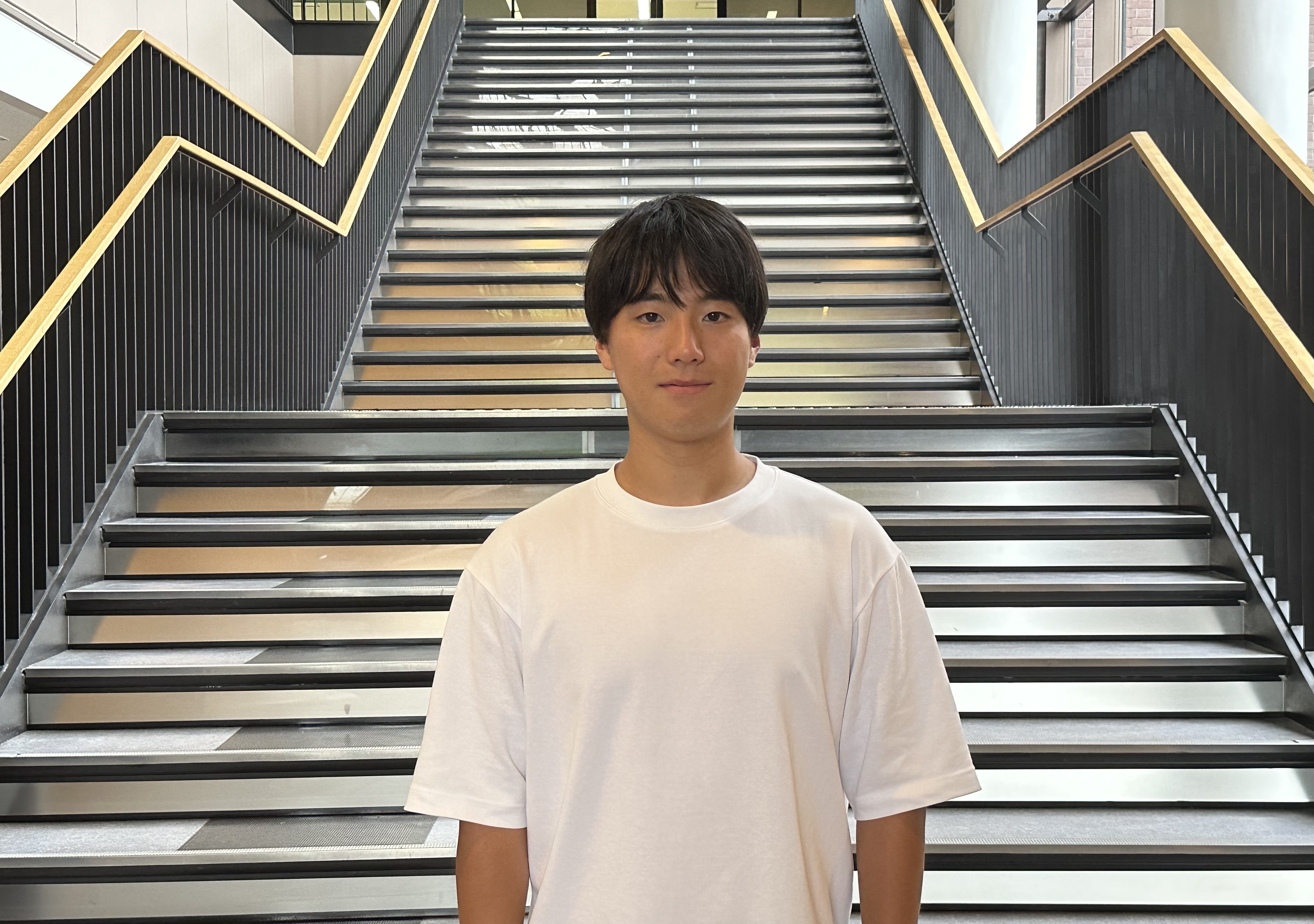
【兼松悠真さんのコメント】
このたび、学士課程での研究成果が論文として採択されましたことを、大変光栄に存じます。
眼窩骨折は発生頻度こそ低いものの、診断が遅れると眼球運動障害などの重篤な機能障害に発展しかねない重要な疾患です。
本研究で開発したAI診断システムは、CT画像から眼窩骨折を高精度に判定し、迅速かつ正確な診断支援を実現できることを示しました。本技術が臨床現場における診断精度の向上と患者予後の改善に寄与することを願っております。最後に、ご指導・ご支援を賜りました先生方、共同研究者の皆様に心より御礼申し上げます。
【奥拓明医師(京都府立医科大学)のコメント】
眼窩骨折は外傷を契機に発症し、複視によって日常生活の質(QOL)が著しく低下する可能性のある疾患です。しかしながら、本疾患は医療従事者の間でも十分に認知されておらず、外傷診療を専門とする医療機関や放射線科医においても、しばしば見逃されることがあります。特に閉鎖型骨折では、外直筋や眼窩脂肪が骨片に挟まれることにより、顕著な眼球運動障害や嘔気・嘔吐を呈します。臨床の現場では、これらの症状が打撲による脳震盪と誤診され、治療開始が遅れる症例を多く経験しております。
本研究では、AI技術を活用することで、眼窩領域に不慣れな医師でもCT画像から閉鎖型骨折を見逃さずに診断できることを目指しております。AIモデルの構築には多数の学習症例が必要であり、そのためには多施設共同での症例収集が一般的ですが、多施設化によりデータの均質性や診断精度に課題が生じることもあります。
その点、当院では過去10年間にわたり1000例を超える眼窩骨折症例を経験しており、本邦においてもこれほどの症例数を有する施設は極めて稀です。本研究成果は、極めて意義深く、学術的にも価値の高い報告であると考えております。今後の課題としてはより精度の高いAIの構築、閉鎖型骨折でも筋絞扼型と脂肪絞扼型の鑑別を行うこと、前向き研究でAIの精度を確認することで、さらに研究を進めてまいります。
最後に、本研究にあたり多大なるご助力を賜りました同志社大学の奥村直毅先生、小泉範子先生をはじめ、同教室の先生方に心より感謝申し上げます。臨床医としての限界は、データ処理や情報技術に関する知識の不足にあると痛感しておりますが、今回このような研究を、同志社大学の皆様と共に推進できたことを大変光栄に思っております。
本研究の詳細な内容は、以下をご覧ください。
タイトル
Hierarchical Deep Learning System for Orbital Fracture Detection and Trap-door Classification on CT Images
著者
Hiroaki Oku*, Yuto Nakamura*, Yuma Kanematsu*, Ayumu Akagi, Shigeru Kinoshita, Chie Sotozono, Noriko Koizumi, Akihide Watanabe, and Naoki Okumura
* 共同第一著者
関連情報
PMID: 40644886
| お問い合わせ |
生命医科学部・生命医科学研究科事務室 TEL:0774-65-6020
|
|---|
生命医科学研究科 医工学・医情報学専攻 バイオメカニクス研究室の八木愛花さんが、2025年5月31日~6月1日に日本大学工学部で開催された第74期学術講演会の発表で、日本材料学会優秀講演発表賞を受賞しました。

【八木愛花さんのコメント】
この度、優秀講演発表賞をいただくことができ、大変光栄に思います。
廃棄物であるパイナップルの葉を有効活用した複合材料の開発は、環境負荷の低減につながると期待しています。
発表題目
「パイナップル葉繊維/バイオベースポリアミド樹脂の機械的特性に及ぼす繊維へのアルカリ処理の影響」
連名者
八木 愛花(生命医科学研究科 医工学・医情報学専攻 医工学コース 博士課程(前期課程) 2年次生)
田中 和人(生命医科学部 医工学科 教授)
藤井 透(TRAMI, 同志社大学 先端複合材料研究センター)
渡辺 公貴(生命医科学部 医工学科 教授)
川口 正隆(生命医科学部 医工学科 教授)
| お問い合わせ |
生命医科学部・生命医科学研究科事務室 TEL:0774-65-6020
|
|---|
生命医科学研究科 医工学・医情報学専攻 バイオマテリアル研究室の吉村柚香さんが、2024年12月14日~15日に横浜国立大学で開催された日本機械学会第35回バイオフロンティア講演会の発表(内容に関しては若手優秀講演賞受賞時の報告参照)で、日本機械学会若手優秀講演フェロー賞を受賞しました。

【吉村柚香さんのコメント】
このたび、日本機械学会若手優秀講演フェロー賞という大変名誉ある賞をいただくことができ、大変光栄に思っております。
学部時代から取り組んできた本研究テーマは、うまくいかずに悩むことや苦しい時期もありましたが、こうして評価していただけたことをとても嬉しく感じています。
日頃よりご指導いただいている森田教授、山本教授をはじめ、切磋琢磨しながら共に研究に励んできた研究室の皆さん、そして本研究に関わってくださったすべての皆様に、心より感謝申し上げます。
発表題目
「ゼラチンマイクロ粒子混合によるPLLAスキャホールドの細胞接着性改質」
連名者
吉村 柚香(生命医科学研究科 医工学・医情報学専攻 医工学コース 博士課程(前期課程) 1年次生*)*:発表時の学年、現2年次生
中川 脩 (生命医科学研究科 医工学・医情報学専攻 医工学コース 博士課程(前期課程) 2年次生*)*:発表時の学年、現博士課程(後期課程) 1年次生
山本 浩司(生命医科学部 医工学科 教授)
森田 有亮(生命医科学部 医工学科 教授)
| お問い合わせ |
生命医科学部・生命医科学研究科事務室 TEL:0774-65-6020
|
|---|
2025年6月12日、吉田創志さん(生命医科学研究科 医工学・医情報学専攻 脳神経行動工学研究室)が、村田学術振興・教育財団の研究者海外派遣援助に採択されました。
本助成は、日本の学術および文化の向上・発展に資する研究に対し、海外で開催される国際会議等での研究発表を支援することを目的としています。吉田さんは、コウモリのエコーロケーション行動に関する研究成果を、9月にデンマークで開催される国際生物音響学会にて発表する予定です。
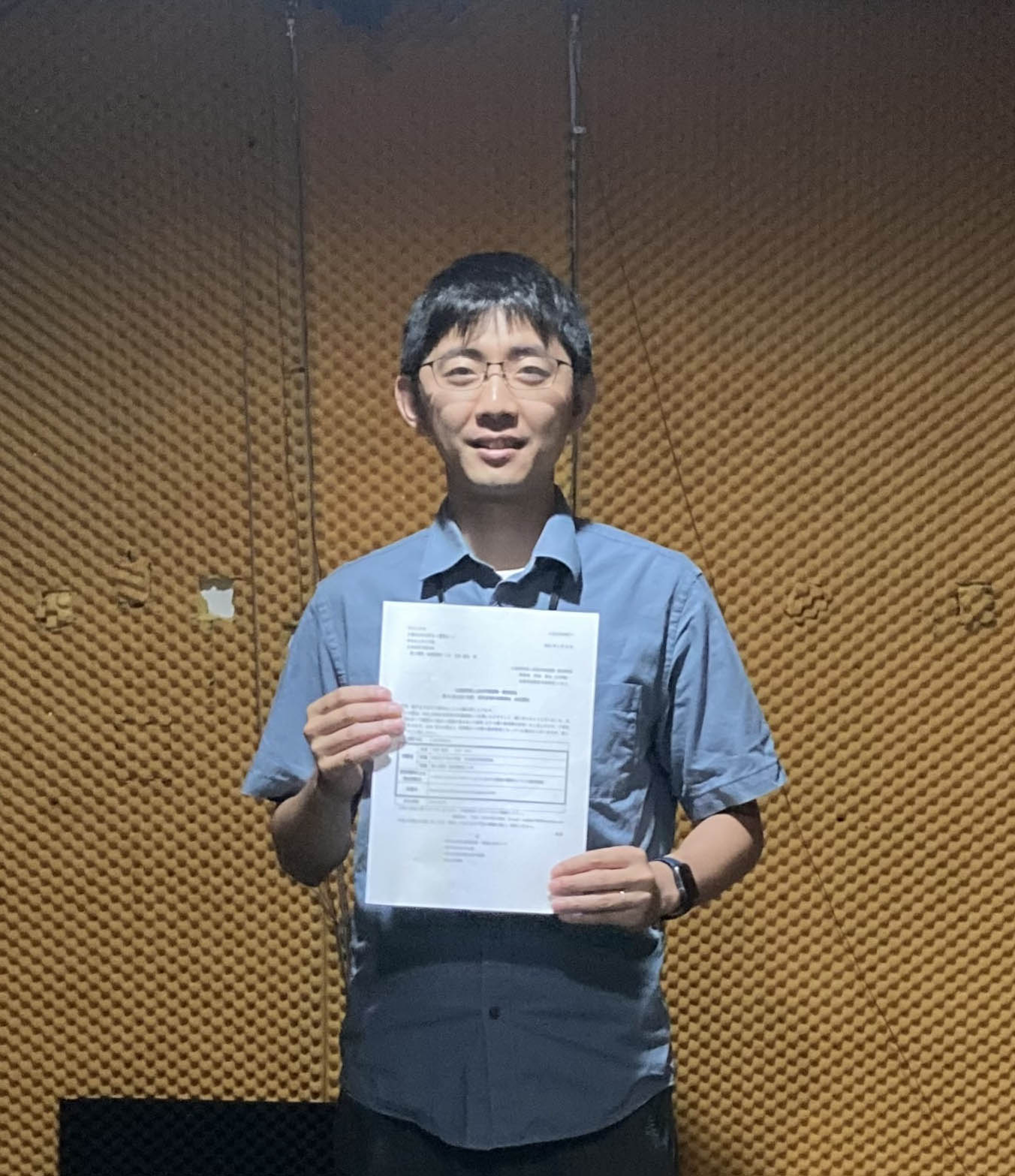
| お問い合わせ |
生命医科学部・生命医科学研究科事務室 TEL:0774-65-6020
|
|---|
新家一樹さん(生命医科学研究科 医工学・医情報学専攻 脳神経行動工学研究室)が、2025年度の公益財団法人 日本科学協会の笹川研究助成生物学部門に採択されました。
同助成は、課題の設定が独創性・萌芽性をもつ研究、発想や着眼点が従来にない新規性をもつ研究を支援することを目的としており、大学院生だけでなく任期付き雇用の助教など35歳以下の若手研究者を対象としています。新家さんは「微小管結合タンパク質MAP2の機能消失がもたらす『めまい』のメカニズムを解明」を研究テーマとして助成に採択されました。
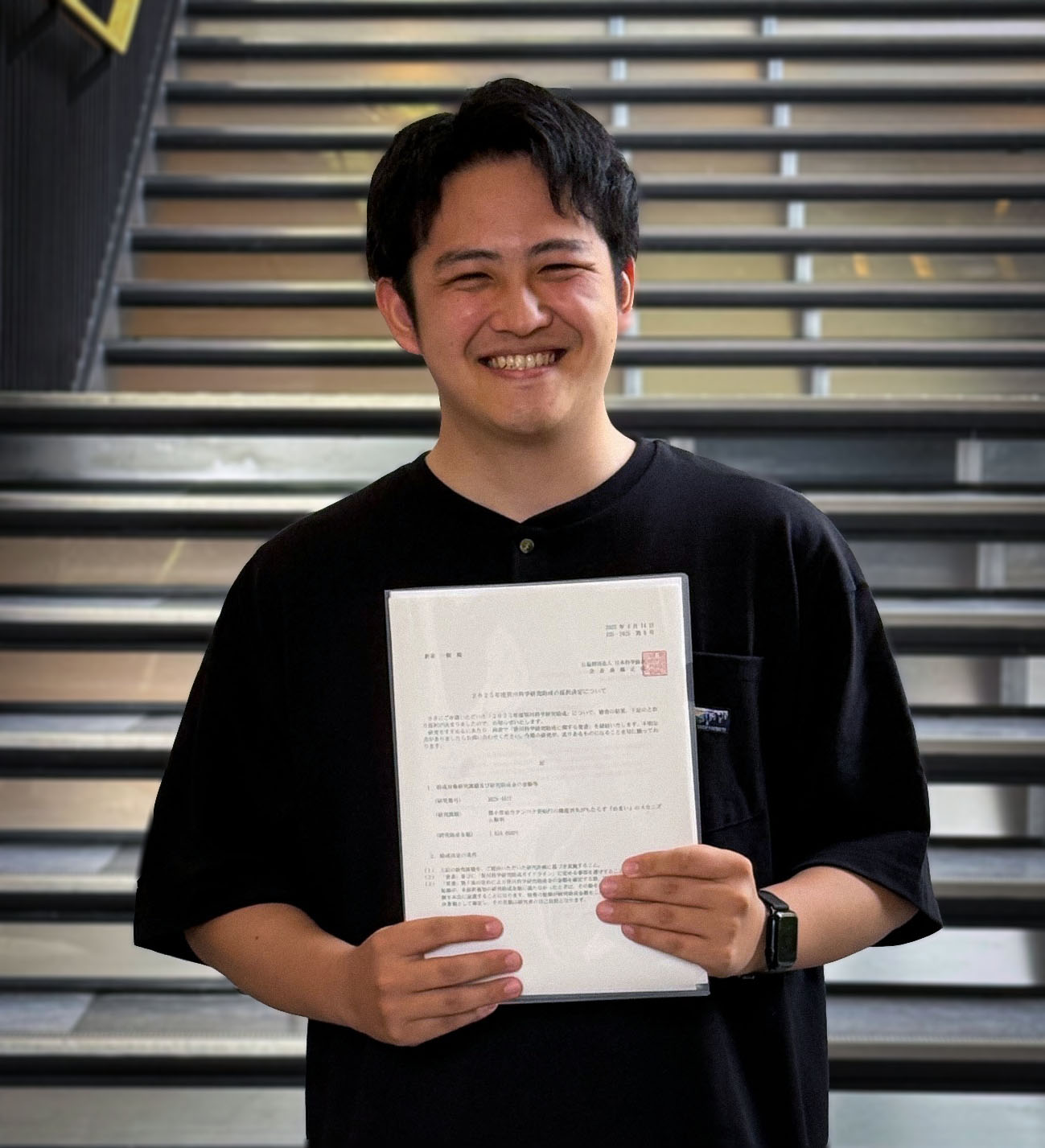
| お問い合わせ |
生命医科学部・生命医科学研究科事務室 TEL:0774-65-6020
|
|---|
生命医科学研究科 医生命システム専攻 分子生命分野 安西聖敬さん(2022年度修了)、髙橋美帆助教、西川喜代孝教授らの研究成果が、Communications Biology誌に掲載されました。
骨の恒常性は、破骨細胞による骨破壊と骨芽細胞による骨形成のバランスで維持されており、このバランスが骨破壊側に傾くと骨粗鬆症や関節リウマチなど様々な骨破壊疾患が引き起こされます。そこで、破骨細胞の働きを抑制できればこれら疾患の治療につながると期待されます。安西さんらは、造血幹細胞から破骨細胞への分化を効率よく阻害する多価型ペプチド、WHD-tetを開発しました。さらに、WHD-tetはマウスを用いた骨破壊モデルでも効率よく骨密度の減少を抑制することを見出しました(図1)。
造血幹細胞が破骨細胞に分化するためには、破骨細胞分化因子であるRANKLが細胞表面に存在するRANKに結合することが必須です。この時、RANKの細胞質側にアダプター分子であるTRAF6が会合し、分化に必要な様々なシグナルが発生します。これらシグナルの重要性は分化段階によって異なります。安西さんらは、WHD-tet は分化の非常に遅い段階で働くこと、この時RANKとTRAF6の相互作用を絶妙に調節することによって、MKK3と呼ばれるキナーゼのTRAF6へのリクルートのみを特異的に阻害し、最終分化に必要なシグナルを効率よく抑制していることを見出しました(図2)。WHD-tet はタンパク質間の相互作用を微細に調節することで下流シグナルの量と質を制御する、新たなタイプの治療薬として期待されます。
研究内容の詳細は以下の関連情報をご覧ください。
関連情報
論文タイトル
Clustered peptide regulating the multivalent interaction between RANK and TRAF6 inhibits osteoclastogenesis by fine-tuning signals
著者
Anzai M., Watanabe-Takahashi M., Kawabata H., Masuda Y., Ikegami A., Okuda Y., Waku T., Sakurai H., Nishikawa Ke., Inoue J., and Nishikawa K*
*Corresponding author
雑誌
Communications Biology, 2025 Apr 22;8(1):643
doi: 10.1038/s42003-025-08047-2

| お問い合わせ |
生命医科学部・生命医科学研究科事務室 TEL:0774-65-6020
|
|---|
生命医科学研究科 医工学・医情報学専攻 バイオマテリアル研究室の出口航至さんが、2025年5月24日~25日に慶應義塾大学日吉キャンパスで開催された第37回バイオエンジニアリング講演会において、優秀ポスター表彰を受賞しました。
出口航至さんは、ヒトiPS細胞由来心筋スフェロイドに対する接触変形が拍動能に影響を与えるメカニズムに関して、スフェロイド内の局所的な変形が組織全体の電気的興奮と機械的収縮の協調作用を強化することを明らかにしました。この結果から培養心筋組織を移植する際の変形状態が心臓再生医療の治療効果に影響を与える可能性が示唆されました。
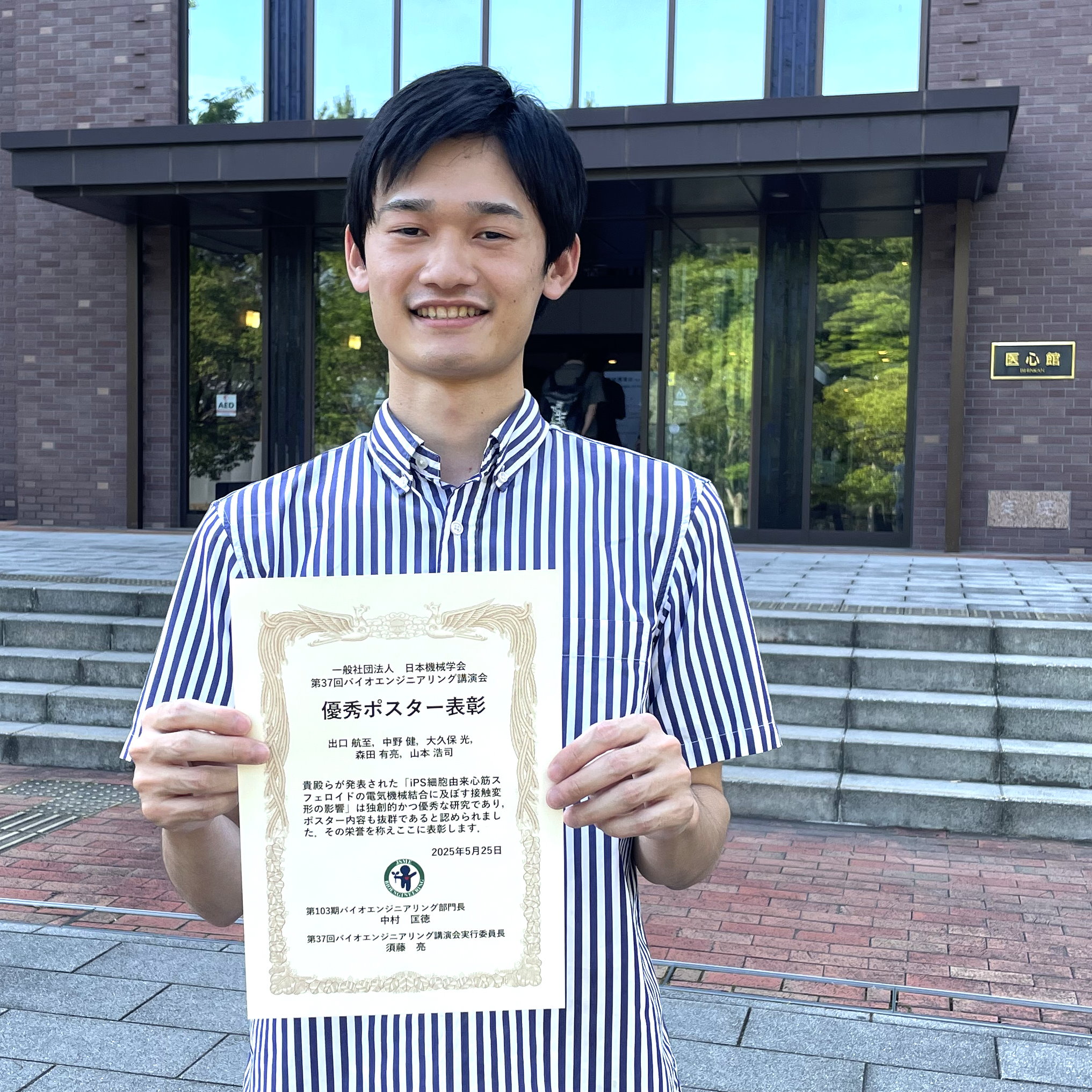
学会から評価していただき大変光栄に思います。
発表の場では多くの先生方から貴重な意見や質問をいただき、大変刺激を受けました。
本受賞を励みに今後も良い報告ができるよう研究を発展させていきたいと思います。
発表題目
「iPS細胞由来心筋スフェロイドの電気機械結合に及ぼす接触変形の影響」
連名者
中野 健(横浜国立大学 大学院環境情報研究院 教授)
大久保 光(横浜国立大学 大学院環境情報研究院 准教授)
森田 有亮(生命医科学部 医工学科 教授)
山本 浩司(生命医科学部 医工学科 教授)
| お問い合わせ |
生命医科学部・生命医科学研究科事務室 TEL:0774-65-6020
|
|---|