サイエンスコミュニケーター養成副専攻~社会と科学の架け橋(学部横断型)~
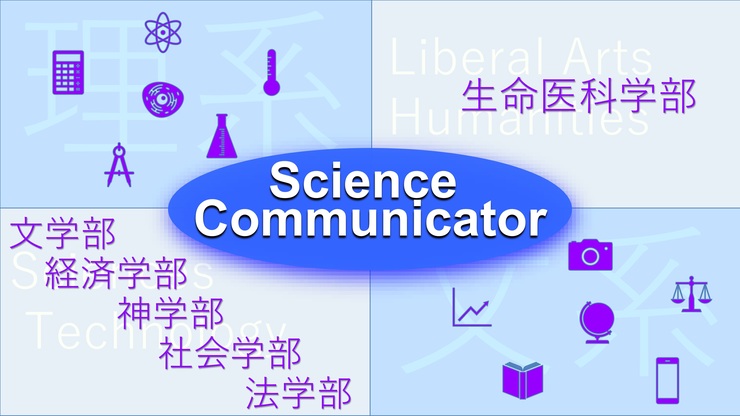
ニュース・お知らせ
-

-

-

-

設立の趣旨
暮らしのすみずみに科学技術が入り込み、社会に混乱や不安が広がっています。地球温暖化と原子力、巨大地震のリスクと防災・減災、遺伝子組換え作物やゲノム編集食品の増加、新型コロナウイルス感染症が引き起こした社会の分断、生成AIによる誤情報の氾濫などは、その象徴的な事例と言えます。
たった一つの答えが存在しないとき、一般の人々はどう対処していいか分からず、不安を感じたり、真偽不明なまま提示された「分かりやすい答え」に飛びついたりしがちです。これからの時代に必要なのは、科学的な考え方を使って目の前の現実を理解し、社会との対話を通じて人々の判断や行動を支援する「サイエンスコミュニケーター」です。
同志社大学は、サイエンスコミュニケーターを育成することをめざし、2016年度、文理横断型の副専攻を全国で初めて開講しました。生命医科学部、神学部、文学部、社会学部、法学部、経済学部の6学部に開かれ、2024年度までに延べ468人が履修しています。
本副専攻では、科学技術に関する基本的な知識を幅広く学びます。新聞・放送・ネットなどのメディアや教育界・産業界・官庁・アカデミアなどから多彩なゲストを迎えてのオムニバス講義が受講できます。異なる学部の学生たちとの交流を通して表現力、プレゼンテーション力が鍛えられ、就職活動など将来のキャリアパスの選択肢が増えることが期待されます。企業や病院・福祉施設への短期インターンシップ「ビジネスワークショップ/メディカルワークショップ」では、社会のさまざまな現場で働く人たちとつながる経験ができます。
プログラムの特色
- 基本設計
本副専攻は、主に2,3年次生を対象にした「少人数制教育」を軸としていることから、定員を設けて履修生を選抜しています。
- 必要単位
修了に必要な単位は20単位であり、4年次生終了までに副専攻が提供しているサイエンスリテラシー科目を12単位以上、協力学部からの提供科目で開講されているコミュニケーター関連科目を8単位以上修得することが、認定の要件です。
紹介動画
教員紹介 (*サイエンスリテラシー科目群担当)
サイエンスコミュニケーター養成副専攻の履修について
本副専攻は6学部(生命医科学部、神学部、文学部、社会学部、法学部、経済学部)の2年次生以上に開かれています。
サイエンスコミュニケーター養成副専攻履修に関するガイダンス
※副専攻の履修が決定した学生は、サイエンスコミュニケーター養成副専攻科目(サイエンスリテラシー科目群の科目)を科目登録する前に、下記履修ガイダンスの内容を再度確認してください。
動画 サイエンスコミュニケーター養成副専攻に関する履修ガイダンス(2025年3月14日公開)
2025年度 募集について【神学部、文学部、社会学部、法学部、経済学部生の場合】
詳しいことは、所属する学部のウェブサイトを参照するか、事務室に問い合わせて下さい。
【参考情報】生命医科学部以外の2025年度サイエンスコミュニケーター養成副専攻申請期間
※申請方法その他詳細(申請締切日の時刻含む)につきましては必ず所属学部に確認してください。
2025年度 募集について【生命医科学部生の場合】
| 提出先 (ウェブサイト経由) |
サイエンスコミュニケーター養成副専攻志望理由書提出サイト(https://webdisk.doshisha.ac.jp/public/glpTQggNPlXSkSfKj8d0qv69PGpPxklisc5gPaq1cZkr) ※ファイル名は【学生ID・志望理由書】とすること。(例)111424XXXX・志望理由書 |
|---|---|
| 志望理由書の 受付期間 |
2025年3月18日(火)~3月26日(水)17:00【厳守】 ※締切日時までに受信したデータのみ有効 ※理由書のダウンロードもこの期間に行ってください。 |
| 履修対象・定員 | 対象:2年次生以上/定員:50名(予定) |
| 志望理由書記入にあたっての注意事項 | 累積GPAおよび修得単位数は最新(2025年3月時点)の値を記入する。 |
| 選考結果 | 3月28日(金)までにDUETのメッセージ機能を通じて発表します。 ※昨年度までに履修を申請し、許可を得ている場合は再度申請する必要はありません。 |
| その他注意事項 | 「サイエンスリテラシー科目群」の科目は副専攻履修許可者のみが登録履修できます。 副専攻履修許可者以外がサイエンスリテラシー科目群の科目を登録した場合は、登録エラーが表示されていなくてもエラー修正期間中に強制削除されます。 |
副専攻科目の登録について
2025年度認定科目一覧
2025年度スケジュール・時間割
2025年度シラバス(サイエンスリテラシー科目群)
先行登録と登録志望理由書の提出が必要な科目
「先行登録」は学習支援システム(DUET)から行うこと。
受付期間 3月29日(土)10:00~4月1日(火)17:00
取材・インタビュー実践講座・未知型探索ビジネスワークショップ 登録志望理由書
提出先 「取材・インタビュー実践講座・未知型探索ビジネスワークショップ 登録志望理由書」提出サイト(https://webdisk.doshisha.ac.jp/public/XlZQQ8GN_lXTvSKc5nEWyk26gBrUuIrcHzJ0xYLjRFA7)
※ファイル名は【学生ID・(取材・未知型)登録志望理由書】とすること
受付期間 3月29日(土)10:00~4月1日(火)17:00
先行登録が必要な科目
先行登録は学習支援システム(DUET)から行うこと。
受付期間 3月29日(土)10:00~4月3日(木)17:00
一般登録科目
サイエンスライティング
サイエンスとインテリジェンス (ベイトソン研究)
サイエンスとインテリジェンス (集中読解と議論)
サイエンス・ナウ1 (生命科学とこころの科学)
サイエンス・ナウ2 (生命医科学入門)
サイエンス・ナウ3 (報道と広報の現場)
サイエンス・ナウ4 (放射線、原子力、エネルギー)
サイエンス・ナウ5 (メディカルワークショップ・インターンシップII基礎講義)
サイエンス・ナウ6 (生命科学と社会)
サイエンス・ナウ7 (食、健康、科学リテラシー)
サイエンス・ナウ8 (多様なサイエンスコミュニケーション )
(注意点)
登録についての詳細は、必ず学部ごとの登録要領を確認してください。
過去の活動報告冊子は、各学部の事務室で配布します。
生命医科学部教授
野口 範子

専門
酸化ストレスの科学
副専攻における授業内容
計画を立てて、実際に立ち上げたこの副専攻のコーディネーターが、私の主な役割です。副専攻の説明やガイダンスも行っています。春学期に「サイエンス・ナウ3(報道と広報の現場)」、「ビジネスワークショップ」、そして通年科目の「取材・インタビュー実践講座」「未知型探索ビジネスワークショップ」を担当しています。
興味を持って取り組んでいること
文系と理系に分かれて偏った受験勉強を経て、それぞれの学部に入学してきた学部生に、学部の違いを超えて“科学と社会”について真剣に考え、議論する環境を提供することです。研究室では、約30人の学生、院生と研究に取り組んでいます。研究も同じですが、学生の成長をみながら、自分自身も新しい発見に出会えることが楽しいです。
生命医科学部特別客員教授
元村 有希子

専門
サイエンスコミュニケーションの理論と実践、サイエンスジャーナリズム
副専攻における授業内容
サイエンスコミュニケーションの基礎的な知識を学ぶ「科学技術概論Ⅰ」(春学期)や、「読む・聞く・話す・書く」スキルが身につく「サイエンスライティング」(春学期)「アウトリーチ実習」(秋学期)、外部講師が週替わりで登壇する秋学期の「サイエンス・ナウ7(食・健康・科学リテラシー)」を担当しています。
2025年度春学期からは「サイエンス・ナウ8(多様なサイエンスコミュニケーション)」を開講します。さまざまな場でサイエンスコミュニケーションを実践し、国内外で活躍している話題の講師を招き、その魅力と情熱を語ってもらいます。
興味を持って取り組んでいること
「VUCA(変化、不確実、複雑、曖昧)の時代」と呼ばれる21世紀、科学技術をめぐる環境もめまぐるしく変わっています。最新の成果や先端技術に臆することなく向き合い、その可否を自分なりに判断できる市民が増えるよう、サイエンスコミュニケーションの考え方やスキルを広げていきます。その過程におけるジャーナリズムの役割についても関心を持っています。
生命医科学部教授
池川 雅哉

専門
ゲノム医科学・タンパク質科学
副専攻における授業内容
医学・医療におけるサイエンスコミュニケーションの重要性を学ぶことを目標に授業を組んでいます。南京都病院における神経難病や重度心身障害児病棟訪問、京都医療少年院における更生施設見学と精神科領域の学び、多発性硬化症をはじめとする神経免疫疾患患者さん向けの動画解説の演習などを通じて、履修生には普段目の届きにくいもう一つの医療現場を見て考えていただきたいと思っています。また現代は、大規模災害や感染症などの脅威と無縁ではいられないことから、「非常時の医療」におけるサイエンスコミュニケーションについて考えていきましょう。
興味を持って取り組んでいること
日頃は、アルツハイマー病や心筋症・筋ジストロフィーなどの疾患を対象に、質量分析法という技術を通じて新しい診断・治療法開発に関わる基礎研究に従事しています。一方で、患者さんやご家族の疾患との戦いは、すべてのライフステージに及ぶことから、科学技術の成果を社会に還元することとその方法論としてのサイエンスコミュニケーションは、今日ますます重要性を帯びていると痛感しています。
生命医科学部准教授
齋藤 直人

専門
神経生理学
副専攻における授業内容
「サイエンス・ナウ6」を担当しています。本講義は、日本における生命科学や関連学術分野と社会・倫理・経済との関わりに着目し、生命医科学部教員によるオムニバス形式で行っています。科学は世界共通のものですが、研究となると日本には日本特有の問題や課題があり、私の回では特にそのような視点を伝えています。
興味を持って取り組んでいること
神経細胞の分子の動きを理解する研究を行っています。そのために、顕微鏡を使って神経細胞をしつこく観察しています。観察は自然科学においてもっとも原始的かつ重要な行為ですが、これがなかなか難しい。ですが、きれいに見えたときは感動します。
生命医科学部教授
祝迫 惠子

専門
外科学一般、消化器病学、移植免疫
副専攻における授業内容
春学期の「サイエンス・ナウ2」、秋学期の「サイエンス・ナウ1」を担当しています。サイエンス・ナウ2では、生命科学とは何か、健康・病気とは何か、医療はどのように発展してきたか、などを概説します。さらに、生命科学に関連する社会問題についても学びます。サイエンス・ナウ1では、精神医学の観点からヒトのこころを科学的に概説し、代表的な精神疾患について、概要と治療・対応法について学びます。現代人のこころの問題について理解を深めることが目標です。
興味を持って取り組んでいること
肝臓の研究をしています。自分の研究が、何か患者さんのためになることにつながればよいなと思っています。
近年は、肝臓における免疫細胞の働きに興味を持って取り組んでいます。
社会学部教授
藤本 昌代

専門
社会学
副専攻における授業内容
秋学期の「科学技術概論Ⅱ(2025年度休講)」を担当しています。研究者・技術者が就業する研究・開発組織の調査に長年取り組んできたので、科学技術を生み出す人々が置かれた社会環境に関する話と、社会調査の入門編の授業を「科学技術と社会」に関わるトピックスに特化し、コンパクトにして初学者にもわかりやすく説明します。
興味を持って取り組んでいること
現在は2021年度からOECDのGlobal Partnership on Artificial IntelligenceのFuture of Workの日本チームで半数以上の事例調査を藤本チームで行っています。今年で5年目で、AIの社会実装の過渡期に起こる社会現象を記録し、分析しています。私自身、第二次AIブームの頃に開発に従事していたこともあり、文理融合人材として研究を行っています。
理工学部教授
後藤 琢也

専門
資源・エネルギー学
副専攻における授業内容
現在、世界で利用の利用が加速されつつある原子力について、その意味するところを明らかにすることを目標としています。春学期の「サイエンス・ナウ4(放射線、原子力、エネルギー)」では、原子力利用につながる科学史を踏まえ、科学技術としての原子力が直面する問題について考えます。併せて、地政学的な観点からも考える必要があることを、その時々の事例を交えて皆で考えます。
興味を持って取り組んでいること
資源その場利用による惑星居住やCO2ネガティブを可能にするエネルギーシステムに資する基礎研究を行っております。
ハリス理化学研究所助教
桝 太一

専門
サイエンスコミュニケーション、マスメディア
副専攻における授業内容
春学期「サイエンス・ナウ8」、また通年講義である春学期「取材・インタビュー実践講座」・秋学期「未知型探索ビジネスワークショップ」を主に担当しています。あらゆる面で多様化・複雑化が進む現代社会において的確なサイエンスコミュニケーションを実現するためには、発信側・受け手側双方の特性を、今まで以上に意識して把握した上で最適なサイエンスコミュニケーションを促す必要があると考えています。私の講義では、まず社会の様々な場面で存在する多様なサイエンスコミュニケーションのあり方を認識してもらい、視野を拡げることを目指しまず。また具体例として、自身の研究テーマでもある商業テレビにおけるサイエンスコミュニケーションの現状・特性・課題も紹介していきます。
興味を持って取り組んでいること
マスメディアを通したサイエンスコミュニケーション、特に先行研究が乏しい商業テレビを対象として、その影響力と特性、また多様なサイエンスコミュニケーションの中で担ってきた特異的な役割を、量的・質的に明らかにしようとしています。特に、科学“非”関心層へのリーチに注目しています。
客員教授
佐藤 優

専門
自然科学と精神科学(人文・社会科学)の共通性と差異について
副専攻における授業内容
私は元外交官で、情報収集と分析を担当するインテリジェンス専門家でした。インテリジェンスの世界では文科系と理科系の双方に関する深いレベルの知識が求められることがあります。すべての問題に通暁している人はいません。自分がこれまで知らなかった問題に直面したときに、当該問題の内容を理解し、的確な対策を見出す方法と技法について学びます。
興味を持って取り組んでいること
高校までの学習指導要領はひじょうによく出来ています。ただし、大学入試が文科系、理科系に分かれている弊害で、高校レベルの知識に欠損がない大学生はほとんどいません。ですからできるだけ早く高校レベルの欠損を埋めるとともに、大学レベルの教育での前提となる論理学と哲学史の習得にも力を入れています。また、自然哲学、錬金術、占星術、陰陽道など近代自然科学以前に自然を取り扱った体系知も視界に収めた講義をしています。
過去の活動
本副専攻に興味や関心はあるが、不明な点や不安があるという学生は、遠慮なく担当教員(生命医科学部教授 野口範子)まで問い合わせてください。
問合せ先:nnoguchi@mail.doshisha.ac.jp

